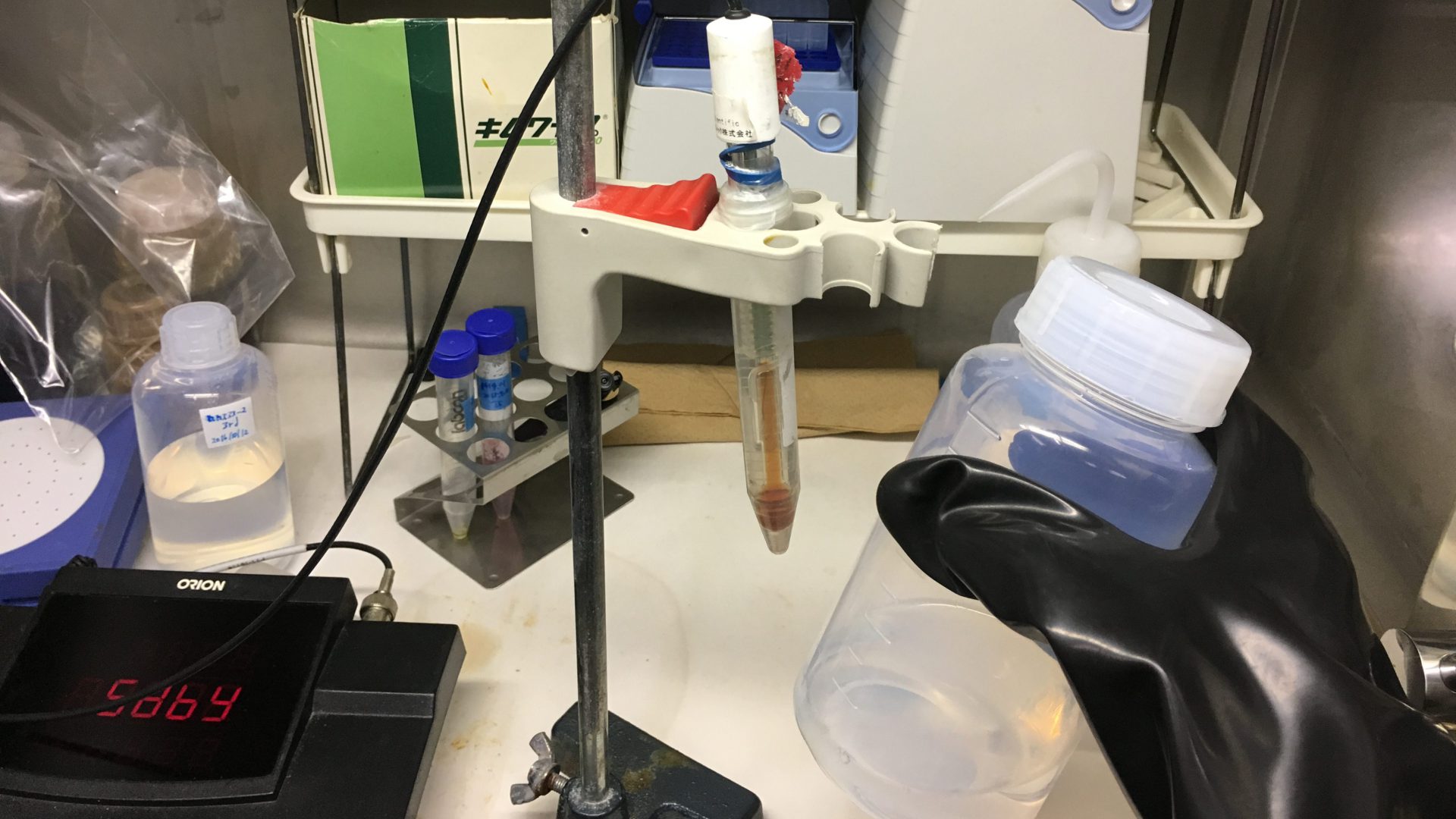深部地下海洋堆積物中の溶存有機物の起源と金属イオンとの結合反応
研究背景と目的: 深部地下水に含まれる溶存有機物(DOM)は,汚染物質や栄養塩の移動に大きな影響を与えます.特に,高レベル放射性廃棄物(HLW)地層処分の安全性評価において,DOMと放射性核種との結合特性の理解が重要です. 表層環境のDOMに関しては多くの研究があり,その特性や起源,金属イオンとの相互作用について,詳細に調べてられています.本研究では、北海道幌延町にある日本原子力研究開発機構の地下研究施設において,さまざまな深度で地下水 […]